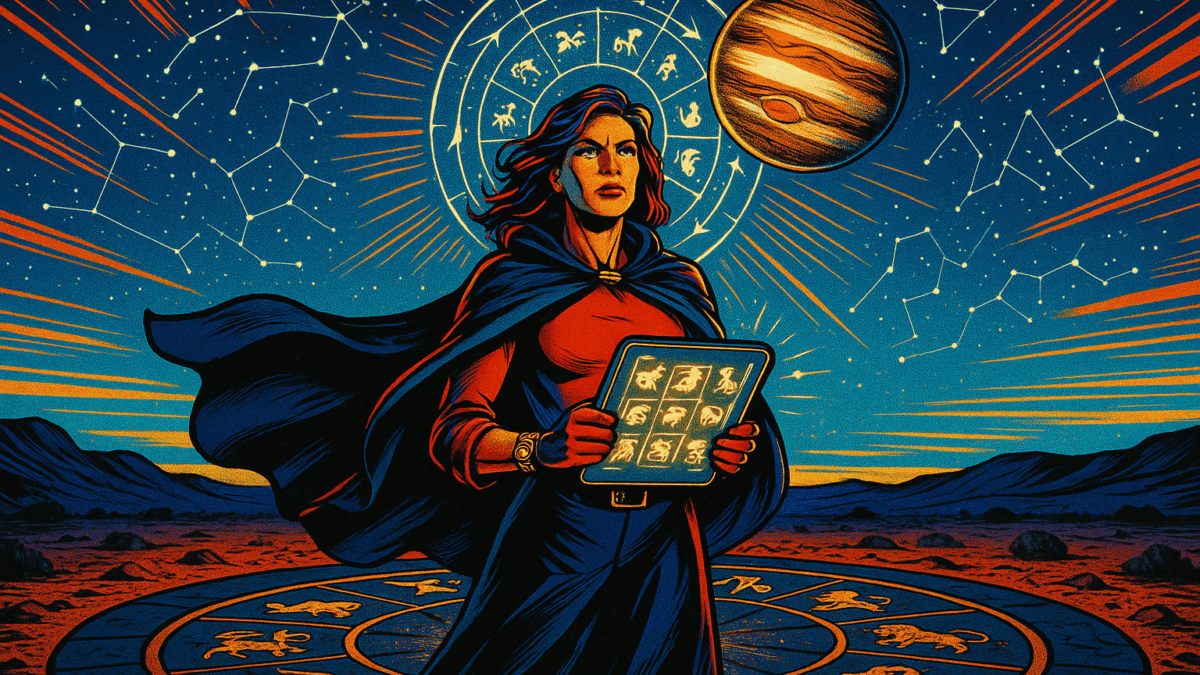十干とは?年・月・日を刻む12の時間サイクル
空間エネルギーを象徴する『十干』に続いて、私たちの人生に流れる”時間のリズム”を司るのが『十二支(じゅうにし)』です。
干支という言葉が示すように、十干と十二支はセットで使われますが、その役割はまったく異なります。
十干が空間の性質を表す”縦の軸”だとすれば、十二支は年月日を表す”横の軸”。
すなわち『時間の流れ』を表すサイクルです。
この章では、十二支がなぜ”12″なのか?どのようにして時間の概念と結びついたのか?そしてそれがどのように私たちの暦や人生にサイクルに影響を与えているのかなどを紐解いていきます。
木星の軌道周期や季節の移り変わりとの関係を知ることで『時間を読む力』が飛躍的に高まるでしょう。
時間とは、ただ流れるものではなく”読めるもの”ーーその感覚を十二支の世界から手に入れてみましょう。
十二支の時間起源は『木星(歳星)』の12年周期
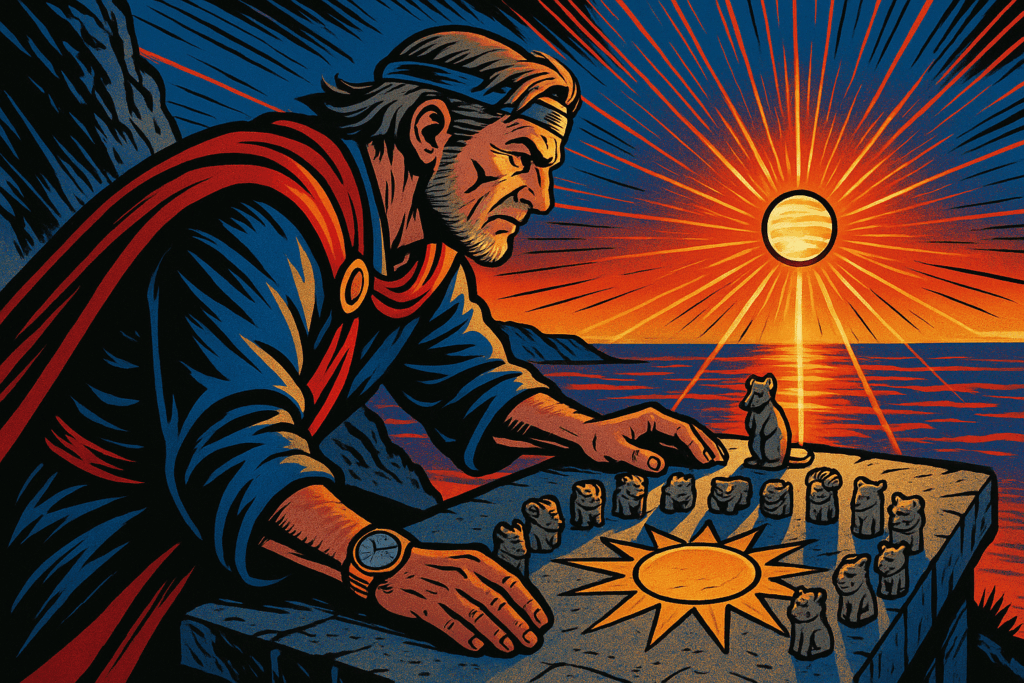
十二支は時間の流れを表す仕組み
十二支とは年月日といった『時間の流れ』を12に区切って表す仕組みです。
この”12″という数字の由来は、ただの数合わせではありません。
古代中国の天文学者たちは『木星(歳星=さいせい)』の運行を観測することで、自然界の数期生を見出し、それを時間の単位として体系化しました。
つまり、十二支とは、『宇宙のリズムを人間の暦に写し取った天の時計』なのです。
木星の公転周期が12年だった
肉眼で観測できる五惑星の中でも、特に木星(歳星)は、その動きが非常に安定していました。
木星は太陽の周りを12年かけて一周し、地球から見たその位置も、毎年ほぼ一定のズレ幅で移動していきます。
古代中国人は、この『12年で一周する星の規則性』に着目し「年の流れを12にわけて管理すれば、自然のリズムにあった暮らしができる」と考えました。
こうして、1年ごとのに1つの記号を当てはめた十二支が生まれたのです。
十二支はなぜ動物名と使うのか?
十二支は『子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥』という動物の名前で表されますが、これは庶民への普及と理解のための象徴化と言われています(諸説あり)。
本来は方角・時間・季節などを意味する抽象記号でしたが、生活の中で覚えやすく親しみやすいよう、動物に置き換えられたそうです。
十二支は木星を起点した時間地図
私たちは日々『ねずみ年』や『うま年』などと気軽に使っていますが、その背景には木星の天体運行という最大な宇宙のリズムが息づいています。
木星の12年周期という天のリズムに従って生まれた十二支は、年月日を読み解くための基準であり、まさに時間を紐解くコンパスなのです。
この12の背景情報を深く理解することで、人生の流れに逆らわず、タイミングを味方につける知恵が手に入るでしょう。
十二支の時間配列と季節
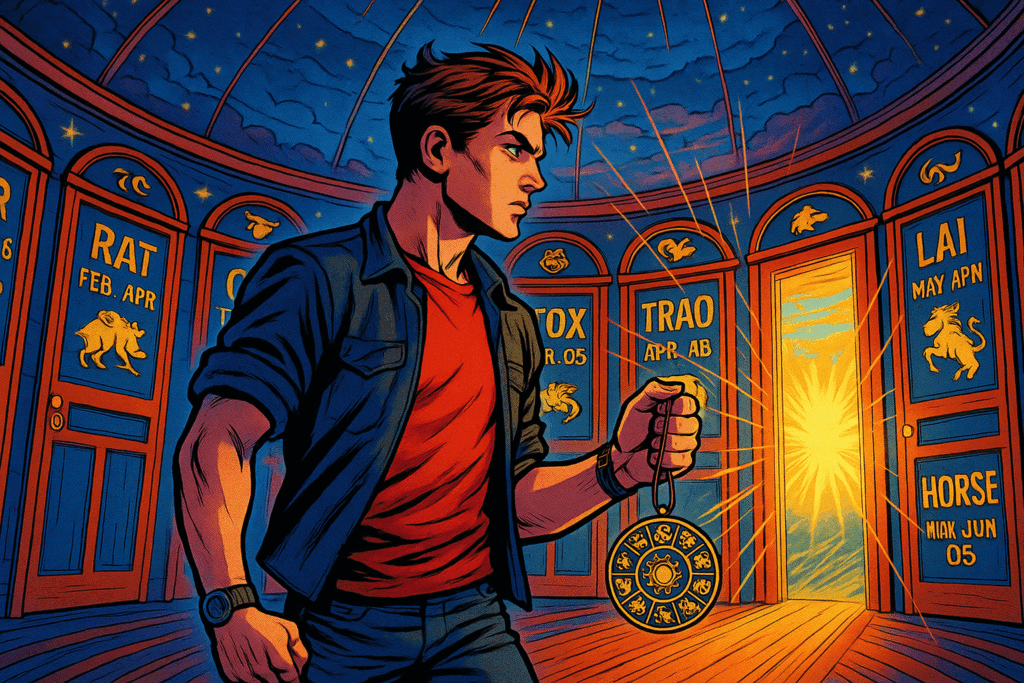
十二支は年月日のリズムを示すコンパス
十二支は、単に”年”を区切る記号ではありません。
1年の中の『月』、1日の中の『時』、さらには人生の『節目』までも12のサイクルで捉える、時間の座標システムと言えます。
各十二支は、季節・時間帯・方位・五行と対応し、私たちの暮らしや行動のタイミングにリズムを与えてくれます。
自然界のリズムは12が最も調和的
古代中国の自然観では、1年の四季や1日の太陽の動き、そして人体のバイオリズムはすべて『12の節目』で動くとされていました
1年=12か月
1日=12の時刻(二時間ごと)
季節=四季をさらに6期に細分化した『節気』
これに対応するように、十二支は以下のような配列で時間を表します。
| 十二支 | 五行 | 月(新暦) | 時間帯 | 方位 | 季節 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子(ね) | 木性 | 12月 | 0時 | 北方 | 冬至 | 黒 |
| 丑(うし) | 土性 | 1月 | 2時 | 北方 | 晩冬 | 黄 |
| 寅(とら) | 木性 | 2月 | 4時 | 東方 | 初春 | 緑/青 |
| 卯(う) | 木性 | 3月 | 6時 | 東方 | 仲春 | 緑/青 |
| 辰(たつ) | 土性 | 4月 | 8時 | 東方 | 晩春 | 黄色 |
| 巳(み) | 火性 | 5月 | 10時 | 南方 | 初夏 | 赤 |
| 午(うま) | 火性 | 6月 | 12時 | 南方 | 真夏 | 赤 |
| 未(ひつじ) | 土性 | 7月 | 14時 | 南方 | 晩夏 | 黄 |
| 申(さる) | 金性 | 8月 | 16時 | 西方 | 初秋 | 白 |
| 酉(とり) | 金性 | 9月 | 18時 | 西方 | 仲秋 | 白 |
| 戌(いぬ) | 土性 | 10月 | 20時 | 西方 | 晩秋 | 黄 |
| 亥(い) | 水性 | 11月 | 22時 | 北方 | 初冬 | 黒 |
このように、十二支は単なる年の記号ではなく、時間の流れそものを示す”環(わ)”の構造となっています。
午(うま)は南・夏・正午の象徴
たとえば『午(うま)』は方位で言えば南方、時間で言えば正午(11時~13時)、季節で言えば夏至前後を表しています。
これは太陽が最も高く登り、陰陽の”陽”が最高潮に達するタイミングでもあります。
この時間帯は、伝達力が高まるとされ、人生を楽しみ、おおらかで明るいなどの性質があります。
一方で『子(ね)』は、真夜中、冬至にあたり、すべてが最も”陰”に傾いた静寂と歳星の時間帯を表しています。
このように、各十二支に宿るリズムと象徴しているものを理解することで、日常の選択や行動を自然の流れに重ねることができるのです。
十二支を読み込み自然のリズムにのる
十二支は単なる占いの道具ではなく、時間を感覚的に捉えるための循環システムです。
年、月、日、時という多重のリズムを同時に把握することで、自然界との調和、人間関係のタイミング、行動の”今やるやるべきこと”が明確になります。
つまり、十二支と使うということは『自然に逆らわず、宇宙と共に生きるすべを身につける』ことなのです。